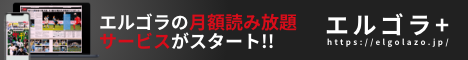
サッカー専門新聞ELGOLAZO web版 BLOGOLA
サッカー専門新聞ELGOLAZO web版 BLOGOLA最新記事
- [3164号]「決断」に込めた思いがあるー中編ー
- [3163号]「決断」に込めた思いがあるー前編ー
- [3162号]J2J3番記者からの推薦状ー後編ー
- [3161号]J2J3番記者からの推薦状ー前編ー
- [3160号]ROOKIES2026ー後編ー
- [3159号]ROOKIES2026ー前編ー
- [3158号]貫禄の二冠
- [3157号]両校史上初のファイナルへ
- [3156号]新監督たちの素顔
- [3155号]移籍市場2026冬
- [3154号]国立も沸かす
- [3153号] 見逃すな 新Jの新星候補たち
- [3152号] J1 EG AWARD 2025 NEXT BREAK
- [3151号] J1 EG AWARD 2025 BREAKTHOROUGH
- [3150号] J1 EG AWARD 2025 BIG IMPACT
- [3149号]J1 SEASON REVIEW 2025
- [3148号]J1 SEASON REVIEW 2025
- [3147号]J1 SEASON REVIEW 2025
- [3146号]J1 EG AWARD 2025
- [3145号]奪還。宿願の21冠目
- [3144号]最終決戦
- [3143号]それぞれのホーム最終戦
- [3142号]さあ完全王手
- [3141号]ラスト2 一騎打ち
- [3140号]U-17 World Cup REVIEW
- [3139号]FC町田ゼルビア 悲願と万感の初タイトル
- [3138号]夢か 新境地か
- [3137号]決戦の盤面のストラテジー
- [3136号]初冠はすぐそこ
- [3135号]切符は譲らない
[川崎F]筑波大OB・車屋紳太郎「1年生のときは毎試合ポジションが変わった。『また変わるのか』と戸惑ったけど、やるしかなかった(笑)」
関東大学サッカーリーグをもっと知ってもらうために、OB選手が大学時代を振り返る連載企画。7回目の今回は筑波大OBの車屋紳太郎が大学サッカーを語ってくれた。

photo:Atsushi Tokumaru photo:JUFA/REIKO IIJIMA
■プロフィール
DF 20 車屋 紳太郎(くるまや・しんたろう)
1992年4月5日生まれ、23歳。熊本県出身。178cm/70kg。タイケンスポーツクラブ熊本→太陽スポーツクラブ熊本→熊本ユナイテッドSC→→長嶺中→大津高→筑波大を経て今季、川崎Fに加入。ルーキーイヤーながらレギュラーを奪取し、ハリルジャパンのバックアップメンバーにも選出される。2013年ユニバーシアード・カザン大会代表。
――筑波大を選んだ経緯は?
「親から、私立は(経済的に)厳しいから国立に進学してくれと言われていた。そうなると国立しか選択肢がない。だから、もしダメだったら働こうくらいに思っていた。筑波大なら教員免許も取れるし、風間(八宏・現川崎監督、元筑波大監督)さんのもとでサッカーができると思って受験した」
――大学4年間を振り返ってみていかがでした?
「人生で初めて一人暮らしをした。大学生というのは高校生と違って自主性を重んじるところ。空いた時間もしっかりトレーニングに使うなど、いろいろと自分で考えて行動することが必要だと思う。僕もそれほど真面目にやっていたわけではないけど(笑)。授業も自分で組んで、親にも頼らずに過ごす。何でも“自分でやる”ことが大事になってくるので、そこは意識してやっていた。そうしたなかでも、遊ぶことよりサッカーを一番に考えていたし、何より周りがそういう集団だった。今あらためて振り返ってみると、そういうチームでやれたことがすごく大きかったと思う」
――筑波大はサッカーに取り組める環境だったと。
「大学自体もスポーツに力を入れていたし、体育学部もあって、サッカーコートもしっかりしていた。トップチームを支えてくれる他の部員もいたし、環境は整っていた」
――プロを目指すうえで大学に行くメリットはどこにある?
「大学サッカー、特に関東大学リーグはレベルが高いので、そこで4年間戦うことで力を蓄えられる。高卒でプロになっても試合に出られないなら、大学で年間を通して試合に出るほうが経験は積めるし、レベルアップできると思う。また、高校生のときは将来のこと、とくにサッカー選手を引退したあとのキャリアまではあまり考えていなかった。大学ではサッカー以外の、そういう部分も含めて学べると思っている」
――思い出に残っているエピソードがあれば。
「1年のときは結果的に新人賞を取れたけれど、毎試合ポジションが変わった。CBに定着するまでにいろいろと変わったし、間違いなくあれがいい経験になった。『また変わるのか』と戸惑ったけど、やるしかなかった(笑)。突然ポジションが変わるから、正直やりづらさもあったけど、毎試合毎試合切り替えていた。後ろだけやっているよりは前線でプレーをしたほうが技術的にも向上するのは間違いないし、自分の特徴を理解できたことは大きかった」
――いまの筑波大にも一緒に戦った仲間たちが多いが、注目選手は?
「MF三丸拡とDF西村洋平。彼らとは2年くらいずっと一緒にやっていた。三丸は運動量もあるし技術もある。西村は、本当にチームのために頑張れる選手」
――あらためて関東大学サッカーの魅力とは?
「他の地域と比べるとクラブユース出身の選手が多い。僕は高校出身組だったので、ユース組のサッカーは強いと思っていた。そういう選手と高校組が交じり合ってサッカーをできるのが大学サッカーの魅力のひとつ。いい選手がたくさんいるから本当にレベルは高いし、自分自身にとっても勉強になった。その中でもポゼッションを重視するチーム、技術を重んじるチームが多かったと思うので、そこに関しての力は伸びたのかな、と思う」
――最後に、大学サッカーでプレーする後輩へのメッセージを。
「僕は最後の年で(所属する筑波大が)2部に落ちてしまったけれど、後輩たちが1年で1部に戻してくれると思っている。今までサッカーをやってきたなかで、大学時代は本当にいい仲間たちに出会えた。サッカーを楽しむということが一番だと思うので、後輩たちにも大学でのサッカーを楽しんでほしい。その中で自分たちらしいサッカーをしてほしいと思う」
5月16日(土)、17日(日)はJR東日本カップ2015第89回関東大学サッカーリーグの第9節。詳しくは(一財)関東大学サッカー連盟オフィシャルサイトへ!
聞き手:川崎F担当・竹中 玲央奈
(BLOGOLA編集部)
2015/05/13 13:19





